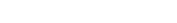補助金の交付について
【お問合せ】 「〇〇市(町・村)□□補助金交付要綱」のような例規なしに、市(町・村)が補助金を交付することは可能なのでしょうか。 【弊社見解】 国の場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化等に関する法律が制定されており、第1条において、「この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の...
「〇〇条例施行規則」に「〇〇条例の施行期日を定める規則」の内容を盛り込めるか
【お問合せ】 本市において、○○条例を公布していますが、附則第1条において施行日を規則で定める日から施行するとしており、現在、〇〇条例は、未施行の状態です。 〇〇条例は、「〇〇条例の施行期日を定める規則」を制定し、施行することを考えています。 しかし、それ以外の必要な事項を規定する「〇〇条例施行規則」を制定する予定があり、〇〇条例の施行日を、当該規則の本文や附則に規定することは...
複数の条例に対応する各規則を一本化することについて
【お問い合わせ】 公の施設の設置及び管理に関する条例を施設ごとに定めており、その条例ごとに規則を定めています。今回規則を一本にまとめてみてはどうかという案が出ています。今までの規則を廃止し、複数の条例を一本の規則で補足することは、法制執務上問題ないでしょうか。 【弊社見解】 複数の条例に対して一つの施行規則を定めてはならないという明確なルールが存在しているかと言えば、法制執務に...
細分ア、イ、ウと細分イ、ロ、ハが混在していること/段階的に用いることについて
【お問合せ】 当町の例規は細分の表記として「ア、イ、ウ」と「イ、ロ、ハ」が混在している状況です。ある条例では「ア、イ、ウ」、別の条例では「イ、ロ、ハ」を用いています。 このように細分が例規ごとに異なる運用は問題ありますでしょうか。 また、ある要綱では、細分「ア、イ、ウ」、細々分「(ア)、(イ)、(ウ)」の後に、さらに細々々分として「イ、ロ、ハ」を用いているものがあります。このように細...
一時的な特例規定を設ける方法について
【お問合せ】 当市では、保険料の減免規定を条例の本則にすでに設けているが、一時的に(たとえば令和2年1月~令和3年3月)減免の対象を広げたいと考えている。 このような場合、条例の本則に定めている減免規定に追加する方法以外で特例のような規定を設ける方法はないのか。 【弊社見解】 減免規定の定め方によっては、条例によらず、規則や要綱に定めることが可能な場合が...
未施行の条の追加に係る欠番の取扱いについて(地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)に関連して)
【ご質問】 今回地方税法の一部改正法の施行に伴い、税条例を改正することとなりました。今回の改正内容は、制定附則第21条の次に附則第22条、第23条及び第24条の3条を加えるものですが、施行期日については第22条と第24条が公布の日、第23条が平成24年1月1日となっています。重要なのは、施行していない規定は通常溶け込んでいないのですが、今回の施行日どおりに溶け込ました場合、真ん中の条である第23...
「法制執務 用字用語早見表」を作成いたしました。
【平成24年8月30日更新】 【令和2年7月21日更新】 規定文を書いていて、「用法はこれで合っていたかな。」 「この場合に句点は必要だったかな。」 と気になって、手が止まってしまうことはございませんでしょうか。 このようなときに、よくある注意点について、簡単に確かめられるような一覧表を作成してみました。 用字用法、句読点の用い方、同音異義語、よくある誤字等について簡潔に記載し...
一括条例の場合の、条例番号について
【ご質問】 二つ以上の条例を一つの本則で改正、公布する場合の条例番号について質問いたします。 二つ以上の条例を同時に改正して、一つの本則で公布するわけですが、この時、条例番号はどのように付けるのが適切なのでしょうか? それぞれの改正条例に改正条例番号が与えられる。 「○○条例等の一部を改正する条例」として一つの条例番号が与えられる。 (この際、同じ条例番号の例規が複数できるので...
「準用読替」と「読替適用」
【お問い合わせ】準用読替と読替適用の違いはどのようなものか。また、表現上どのような違いがあるのか。【弊社見解】<参考文献>『ワークブック法制執務』(法制執務研究会編 ぎょうせい)(p718)『分かりやすい法律・条例の書き方』(磯崎陽輔著 ぎょうせい)(p87~96)『法制執務ハンドブック』(大島稔彦著 第一法規)(p218・219) 「準用」というのは、類似する事象について一々規定を設けることはか...
備考での特例措置規定
【お問い合わせ】 条例の一部改正についてですが、期限付きの特例措置を規定する場合、原始規則の附則に追加するのが普通の考え方と思いますが、別表の備考に追加して規定する方法もありかなと思うのですが、いかがでしょうか。【弊社見解】 表に(注)又は(備考)が付けられることがあるが、これらは、表の中に用いられている語句の定義や表を適用する場合の留意事項、細則等を規定する場合に用いられる。『ワークブック法制執...